『食事姿勢について』
今回は、当施設での取り組みの一つをご紹介します。入居されている利用者様がお食事を安全に楽しく召し上がって頂けるように、特養全体として「食事姿勢のポジショニング」について積極的に取り組んでいます。
※姿勢が崩れた状態で食事を食べ続けると、むせ込みや誤嚥(ごえん)・窒息などにつながってしまう場合もあり、時として命に関わる危険な状態になることもあります。
●当施設での現状
特養で生活されているご利用者様の大半が、いわゆる標準型車椅子で過ごされています。ご自身で椅子に座り換えができる利用者様もいますが、多くの方が椅子や車椅子へ座り換えるためには介助を必要とします。また、ご利用者様の中には、ご自身で車椅子を自走できる方もいらっしゃいます。全ての方が椅子へ座り換えてしまうと利用者様が移動したいときに、直ぐに対応できないため、現時点では車椅子で食事を召し上がっている方も多くいらっしゃいます。
●限られた環境で限られた資源を活かした取り組み
ご利用者様の身体状態は一人ひとり違うため、その方に適した車椅子を使用できるとは限りません。また、身体に合うクッションや介護用のクッションの数にも限りがあるため、限られた環境で限られた資源を活用し、姿勢が崩れないように対応しております。車椅子は、椅子にタイヤがついた移動補助具ですので、食事を召し上がる時には、きちんとした姿勢を提供する必要があります。そのため、椅子で食べたときと同じように、必要最低限のクッションを適切に合わせ調整することで、できるだけ正しい食事姿勢に近づけ、利用者様自身で姿勢を保ちご自身で食事を召し上がることができるよう姿勢を整えております。
●姿勢の変化に気づけるように意識を高める
ご利用者様の中には、最初に姿勢が保持できていても、食事をすることで身体が動き、時間経過と共に徐々に姿勢が崩れてしまう利用者様もいらっしゃいます。そのような方に対しては、お声がけをしながらその都度、姿勢を整えさせて頂き、崩れた姿勢で食事を食べ続けることがないようサポートさせて頂いております。


![yjimage[1]](http://villatopia.org/blogs/rigaku/wp-content/uploads/sites/7/2018/02/yjimage1.jpg)

 ★ 骨折が治る日数(おおよその目安) ★
★ 骨折が治る日数(おおよその目安) ★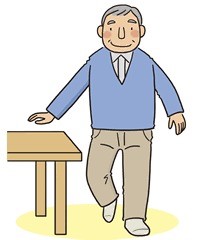


 だいぶ寒くなってきました。寒くなると筋肉がこわばり、体が動かしにくくなります。そのため、10月以降は骨折が増えるとも言われています。これからますます寒くなるので、転倒には注意が必要です。骨折は、骨が折れる原因や折れ方(方向)により治癒過程が長くなったり短くなったりします。今回は、その骨折について少し詳しくご説明させて頂きます。
だいぶ寒くなってきました。寒くなると筋肉がこわばり、体が動かしにくくなります。そのため、10月以降は骨折が増えるとも言われています。これからますます寒くなるので、転倒には注意が必要です。骨折は、骨が折れる原因や折れ方(方向)により治癒過程が長くなったり短くなったりします。今回は、その骨折について少し詳しくご説明させて頂きます。






